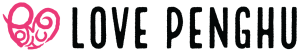澎湖(ポンフー)が誇る伝統文化「踏涼傘」
沖縄や台湾で「涼傘(liáng sǎn|リャンサン)」という傘を見たことがありますか?
涼傘はその名の通り傘の一種なのですが、ふつうの傘とは形が異なり、てっぺんがほとんど平らで、そこから垂直に布を垂らした円柱状の形をしています。
もともとは日よけのための扇子のようなものから発展し、やがて現在の涼傘の形ができ、国王などの高貴な人が歩くときに使われるようになりました。また、涼傘の色や模様はその人の地位によって異なったそうです。

澎湖(ポンフー)の伝統芸能「踏涼傘」とは?
やがて、神様を悪い『気』から守るためにも使われるようになり、神様が廟(お寺)から出たり入ったりするときには、必ず涼傘を持った人が涼傘を持って先導に立ち演舞をするようになりました。
それが「踏涼傘(tà liáng sǎn|タァリャンサン)」です。しかし、時代の流れによって踏涼傘はその形をどんどん簡単にしていき、今では本来の踏涼傘はほとんど見られなくなりました。
踏涼傘では1人または2人が神様に向かって演舞をします。神様に見せるためのものなので、涼傘を持った人は失礼のないように常に体を正面に向けています。
また、基本的な動きには足を開き腰を落とす「馬步」と、片足で立ちもう片方の足を上げる「金雞獨立」が有り、移動する時に足で地面の土を払いのける動作も踏涼傘の特徴的な動作です。
踏涼傘は一見すると単純で簡単に見えるのですが、これを正しい姿勢でこなすには体の柔らかさと筋力が必要で、一朝一夕にできるようなものではありません。
残念ながら、踏涼傘は時代の流れによってその形をどんどん簡単にしていき、今では本来の踏涼傘はほとんど見られなくなりました。
そんななかでも、澎湖には昔ながらの踏涼傘が受け継がれているため、踏涼傘は澎湖を代表する伝統文化となっています。

踏涼傘を後世へ受け継いで行くために
一方で、踏涼傘ができる人が少なくなっているという問題もあり、地区によっては踏涼傘ができる人が地元におらず、廟で儀式をする時に大変困ることがあります。そうした時には他の地区から踏涼傘ができる人を呼ぶそうです。
そこで澎湖(ポンフー)の文化局では踏涼傘教室を無料で開き、次世代に引き継げるよう啓蒙に努めています。
教室に行くと、小学生からお年寄りまでが涼傘を持って勇ましく練習している様子を見ることができます。
廟での重要な儀式の時はもちろん、主要なイベントの始まりには踏涼傘が披露されるのが定番です。澎湖は廟もイベントも多いので、踏涼傘を見る機会も多いですよ。
ぼくも一時期、涼傘を習っていました。実際にお寺のお手伝いをさせてもらったことも何度かあり、より一層、澎湖の文化を知ることができてよかったです。
え? 今後はどうするのかって? それは聞かないでください…。